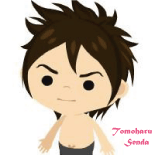2017年は10-20代向けのストリート系雑誌の休刊が相次いだ。
2017年の休刊誌は41媒体。
若者を中心に雑誌が読まれなくなっている。
よく20-40代女性のグループインタビューやデプスインタビューを行っているのだが、本当に雑誌は読まれなくなった。(対象者によるのかもしれないが)
読んでいる人も、美容院で月1回ほど流し読みしたり、本屋に行った時に立ち読みする程度だったりする。
買っているという人をなかなかみる機会がない。
20代だとdマガジンなどの雑誌読み放題のアプリを読んでいる人はチラホラいるが、やはり単体の雑誌を買ってはない。
単純に雑誌からデジタルにシフトしたと片づけてしまえば簡単だが、雑誌を読まないということは他にも色々と影響を与えているような気がしている。
まず、20代-30代前半までの女性に共通するインサイトとして、好きなカルチャーや憧れの不在という問題がある。
これまで雑誌はカルチャーやトレンドを伝えるための役割を担っていて、それぞれの雑誌には世界観があり、周りにはそれを追いかける読者がいた。
生活者は雑誌を通してカルチャーやトレンドを知り、自らのなりたい像を想像し、それに近づけるための努力をした。
雑誌から自らの個性を作り、ある種それが自信にもつながっていたが、いま、雑誌の読み方が変わってきている。
そもそも読まれなくなったのもそうだが、読んでいる一定層の人も、一ページ、一ページ精読するような読み方ではなく、ザッピングしながら読むというテレビのザッピング視聴と同じような読まれ方をされている。
美容院や立ち読みで好きな記事をざざざっとつまみ読み。
dマガジンのような雑誌アプリも"記事単位"でおススメやランキングも出てしまうので、雑誌の表紙から入らなくとも自分に合ったと判断される記事をつまみ読みできる。
そして雑誌アプリで怖いのが、基本的に書籍すべてを読み切るということが行われ辛いところだ。
数百円で数十冊が読み放題。
そりゃ、全部しっかり読み切る人は少なくなる。
ごった煮替えした雑誌群の中から気になるタイトルがついたページだけを読む。
そして、スマホではInstagramやTwitterを中心としたSNSでの一次情報での情報接触が進んでいる。
誰も編集をしていないむき出しのコンテンツに接することがほとんどで、誰かが編集したコンテンツに接することが減少。
いやいやキュレーションがあるじゃないかと言われそうだが、有象無象のキュレーションメディアが乱立し、PV競争ために誇張したタイトル表現によるクリック稼ぎも結構あり、中身すっかすかの記事もいまだに多い。
派手なタイトルを付けた記事や、もともと興味がある記事しか読まれなくなる。
また、雑誌アプリやキュレーションで怖いのが、テキスト文がテキストと認識されず、写真とテキストが一体となって一枚の画像として認識されてしまうことだ。
つまり、頭の中に残りづらいのがデジタルの欠点だったりする。
雑誌を読む時間がデジタルに置き換わったが、これまで雑誌が担っていたカルチャーやトレンドを伝えるという役割は継承されにくくなり、より一層生活者に届きづらくなっている。
基本的に日本人は受け身型のため、与えられたカルチャーやトレンドに乗っかるのは得意だが、自分で見つけていくことは難しい。
行き着くのは、自分の拠り所とするカルチャーやトレンドを持てず、その延長で自らのアイデンティティを確立できず悩む女性が増えていることだ。
自分らしさを持ちたいが、それが何なのかわからない。
どう生きたら良いのかの指針がない。
そう答える女性が意外にも多い。
その背景に、女性の社会進出に伴い、会社と家庭を両立しているロールモデルとなる女性がまだ少ないと感じることが原因にあるかもしれない。
あと、個人的な見立てとしてはこの傾向が大きくなると、より消費行動が消極的になってしまうことに繋がるのではと思っている。
自分らしさや生き方の指針があれば、その旗に向かって人はまっすぐ漕いで行くが、その指針が無ければ漕ぐことができない。
ファッションやコスメ、お出かけ、恋愛など、いろいろなものにどこかちょっとしたブレーキがかかる。
私このままで本当に良いんだっけ、と立ち止まって考え込んでしまう。
雑誌を読まなくなった。スマホに置き換わった。
という現象だけでなく、その延長にある消費行動にも影響を与えており、より生活者は慎重になり、お金を使わなくなっているのではないか。
望むのは、雑誌に置き換わる新しいメディアがデジタルから生まれることだ。
自分を見つけることができるコンテンツがいま、生活者からは求められている。