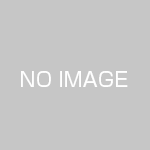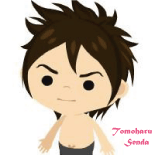女性20-40代のメディア接触について定性調査を行うと、ここ最近、Facebookの利用者が非常に少なくなっている感じがする。
数年前までは、LINEとFacebookが主な接触メディアだったが、今はLINE、Twitter、Instagramが主なアクティブ利用メディアとなっており、Twitterがまた人気を復活させている。
女性を対象者とした定量調査では、ソーシャルメディアに投稿せず"見る専門"として利用している数が、Twitterは約半数、Facebookは8割、Instagramも約半数という結果もある。
半分~8割ほどが"見るだけ"の利用だ。
自分も振り返ってみると、Twitter、Facebookとアクティブに利用していたが、徐々に投稿をやめてしまい、Instagramの更新のみへと変わってきている。
一方で、仕事でコミュニケーションプランニングをする際、「SNSでの生活者のクチコミからインサイトを発見せよ」というお達しが上から度々落ちてくる。
基本的にSNSの書き込みを、むやみ適当に探索しても、目からうろこの落ちるような発見なんて絶対ないんだけど。
それでも、多くの人は、SNSには生活者の"本音"が隠れている。そこには通常の調査では出てこないようなビッグファインディングスがきっとある!と信じてやまない。
冷静になれば、半分合っているかもしれないが、半分間違っていることに気付くはずだ。
基本的に、SNSで心の底から本音で情報発信している人は殆どいない。
人はコミュニティの中にいるときは、そのコミュニティ内でどのように自分が見られているかを意識し、そのコミュニティ内で自分を創っている。
皆の前では、カッコよく/可愛くありたいし、憧れるような存在でありたい。
仮に、本当は根暗で人の悪口ばかり頭の中でつぶやいているような人間であっても、明るくオシャレでキラキラした自分を演じていたいものだ。
つまり、そこには本音ではなく、周りからの目という大きなバイアスがかかったうえでの発言になっている。
2ちゃんねるや匿名で投稿し続けているTwitterアカウントのほうがよっぽど本音で投稿している。
周りの目を気にした上での創られた発言がSNSには多く存在する。
SNSは、"最初は"面白いツールだ。
昔からの友人知人、学校や会社の知り合いと繋がることが楽しい。
ただ、コミュニティに属することの楽しさが、いつしかコミュニティ内での投稿に、本音で語れない息苦しさから徐々に投稿頻度が下がり、見るだけのアカウントにかわってしまう。
匿名性を担保した定量調査の方がよっぽど本音を語ってくれるのではないかと、一周回って感じてしまう。
さんざん自分もやっている定性調査も最近あまり信じてはこわいな、とも思った。
広告会社は、提案資料を作ったり意見をまとめるために、同期や周りに座っている社内の人間を捕まえて簡易デプスインタビューを度々行う。
この前、某商品のデプスインタビューを受けたのだが、そこには全然本音がない回答をどうどうとしている自分がいることに気付いた。
コミュニケーションのコンセプト調査について、A案もB案も正直全然違いがわからないものだったが、「直感でいいから」と言われ、直感でA案を選んだ。
「なんでA案を選んだの?」と尋ねられたが、心の中は(いやいや、、A案もB案もどっちも全然違い分からんわ)と思いつつ、「A案は、機能を前面に出してわかりやすかったからこれが自分にあうと思った」と回答していた。
きっとB案を選んでいたら、それらしく回答をしていたと思う。
「B案のボディコピーにもA案の機能の情報が入っているけど、それでもA案を選んだのは何故?」と更に聞かれる。
その後は、もはやモデレーターが喜びそうな言葉を探しながら、無理に言葉を作って答えていた。
「僕は、毎朝習慣でシャワーを浴びており、A案はそのシャワーを浴びた後の爽快感をイメージするようなメッセージだった」とか「その機能からは、よし今日も前向きに頑張ろうと、4月の新生活に感じるような、心がちょっとあがる新鮮な気持ちを想像した」とか口が勝手に応えている。
モデレーターは、なるほどなるほどと答えながら、「前向きに頑張る」「4月の新生活のような新鮮さ」とかメモしている。
(やばい、、全然そんなこと全く思っていない。でも、せっかくデプスインタビューに呼ばれたし、しっかりしたことを答えないと、使えない奴だと思われてしまうかも、、)
という自身の葛藤と共に、デプスインタビューが終わってしまった。
やはり、そこには本音なんてなかった。
山のようにデプスインタビューやグループインタビューを自分もやってきたが、答える側に立ってみると案外そういうことなのかも、と思ってしまう。
人は、目の前にいる人や周りにいる人、属しているコミュニティ内の人を見ながら言葉を選んで発している。
それはリアルの場では特にそうだが、SNSの中でも同じようなものだ。
一定のバイアスを受けていることを前提に、今後もSNSのクチコミを見ていかないといけない。