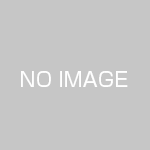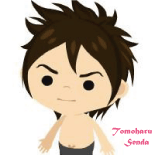一瞬で終わったPayPayの100億円あげちゃうキャンペーンが記憶に新しいが、昨日ファミリーマートが独自のスマホ決済サービス「ファミペイ」を2019年7月に導入することを発表した。
ゆうちょ銀行は2019年2月にゆうちょPayを、KDDIは2019年4月にau Payを、セブンイレブンは2019年夏にセブンペイを導入する。
既に、楽天Pay、LINE Pay、Origami Pay、Amazon Pay、はまPay、…など、○○Payが乱立しているのもあって、ネットでは「スマホ決済増えすぎw」と混乱の声も。
ここまで日本の多くの企業がスマホ決済市場に参入するのは、中国のTencent社が提供する「WeChatPay」の成功が影響しているのだろう。
WeChatPayは8億MAUのモンスター決済サービス。
しかも2013年にリリースしてからたった5年で、中国で爆発的に普及が広がり、現金からスマホ決済が当たり前の市場を創造した。
今さらだが、そもそも「Tencent」と「WeChat」は何か。
Tencentは中国深センで誕生し、SNSアプリであるWeChatを中心に、様々なデジタル事業を展開するインターネットの総合商社のような企業。
中国ではBATと言われるBaidu、Alibaba、Tencentと呼ばれる3大企業の一つで、BATの中でもTencentは50%以上を超えるほどの大きさを持つ。
WeChatは、中国の中では生活者のインフラになっており、SNSやエンタメ、決済、検索、商品売買、行政サービスの支払いもできるほど多くのサービスを網羅している。
凄いなと思うのが、飲食店ではQRを読み取ると番号札をWeChatから取得できたり、子どもの診察予約をWeChatで行い、更に処方箋も受け取れ、それを薬局で提示すれば薬が貰える。
イベントの電子チケットや、旅行のチェックイン・チェックアウトもWeChatで可能。
日本ではここまで幅広くサービスを集約したものはない。
そこから派生したWeChatPayが何故ここまで普及したのか。
もちろん、ベースとして日本と中国の環境の違いはある。
中国では偽札問題が出るなど、現金の信頼性が低いというのがずっと問題視されていたのもあり、信頼できる決済サービスが日本以上に受容性があった。
また、中国政府が金融サービスのリスクを含めてマネジメントしているという背景も大きく、決済アプリのセキュリティを心配しなくてよいという、使用ハードルが低いのも普及を支えるものになっただろう。
そのベースは有りつつも、Tencentが行った非常に卓越したマーケティング戦略があるのだが、ポイントを5つにまとめてみた。
生活インフラとなっているSNSから決済サービスを派生させた
毎日使っているSNSアプリがより利便性を高めたので、そのままユーザーは決済サービスも使いやすかっただろう。
エンタメ、旅行、医療など多くのシーンでWeChatがサービスを広げ、そこで支払いもできるようになれば、より生活者は便利な生活を手に入れることができる。
そりゃ、使わないはずがない。
日本のSNSでは、LINEもLINE Payを展開しているし、ポジションとしてはやや近しいかもしれない。
Tencentの凄さは、そこから利用促進の仕組みをうまく取り入れていったことにある。
文化の中にデジタルをいち早く組み込み習慣化させた
日本と同じく、中国でも旧正月にホンバオ(お年玉)を渡す文化があるのだが、そこにWeChatPayが入ることで、利用活性化を促した。
日本でも正月はポチ袋を準備し、お札を入れて手渡しするという、面倒な文化が続いているが、それがスマホ上で送金できるのは、渡す方は準備も楽になるし、貰う方も誰からいつ貰ったなど管理がしやすい。
ポイントは、スマホ決済を少額でよいので先ず使わせたことであり、一度使うとその利便性を理解するが、その一歩がなかなか踏み出せないものだ。
そこから出産のお祝いに使ったり、遅刻したときの罰金として友人に支払うなど徐々に利用シーンを広げる工夫をした。
確かに出産祝いが置き換わるのはとてもいい。
渡す方も、受け取る方も正直ストレスが大きい。
出産祝いを入れる綺麗な封筒を買って、名前を書いてもらうサービスを店頭で依頼し、新札を準備し、向きを揃えていれ、夫婦そろって手渡しする。
これだけで半日かかる。
受け取る方も、内祝いという文化がある。
頂いた出産祝いの半額ほどを、内祝いとして何か贈り物を買ってお返しする。
これも百貨店に商品を選びに行き、包み紙を選び、住所を書いて送るなど、半日かかる。
そして、出産だけでなく、引っ越し祝い、新築祝い、結婚祝い…などなど、お金と紐づく文化ごとがあるので、それがスマホ決済で置き換わるとなると、とても助かる。
人の気持ちが無くなるという指摘もあるが、逆にこれまでの文化が手間で窮屈に感じる人も一方ではいるので、いつまでもアナログなやり方が好きな人は続ければいい。
ハードとソフトを一緒に普及させた
5年前、中国は日本と違ってタクシーの供給が少なかったのもあり、タクシー配車サービスを行う滴滴に出資するなど、お金を使わせる市場を増やすために企業と積極的に業務提携をしていった。
中国版の食べログであるDianpingと、中国版のグル―ポンであるO2OECと協業し、決済の重要な導線として市場に影響力をもたらしていくなど、ハード(お金を使う市場)とソフト(決済サービス)の両輪で普及を広げていったため、WeChatPayは他社よりも普及速度が速かった。
日本では既にサービス過多な面もあるので、企業に決済サービス機器の導入の方が重要だろう。
VISAカードなど、どこにいっても大体使えるという状況にまで持っていくのが大事だ。
そういう意味ではVISAカードやマスターカードなどクレジットカード会社が決済アプリ市場に参入したほうが、すでに機器の導入が進んでいるので有利な気もする。
オープンプラットフォーム化でロングテールもカバーした
WeChatPayが他の決済サービスと違うのがオープン化を推し進めたところにある。
パートナー企業とAPIを共有し、無償で二次開発する権限を与えているので、Tencent以外の他の企業が魅力的なサービスを開発して普及を広げている。
決済サービスを自販機に組み込んだり、店頭ツールに組み込んだりと普及自体が自走している。
これによって、中小企業が次々と参入し、屋台でQRコードを印刷した紙が貼られているほど、どこにいっても簡単にスマホで決済ができるようになった。
お祭りで買い物をするとき、小銭の準備やお釣りの準備の煩わしさが双方無くなるのもあり、日本でも同じように普及されると生活が変わりそうだ。
また、Tencentは、マクドナルドやタクシー、ドラッグストアなど、電子決済が出来ない業界において、一つひとつ大きな企業と組み、それをPRとして発信することで、大手と中小の両方で導入を広げる工夫もしている。
CRM活動への活用
WeChatPayの強みはCRMにあると思う。
生活者が決済した後に、支払いの受けた企業側から会員勧誘ができたり、企業アカウントをフォローさせたりと顧客とのつながりを作ることができる。
しかも、決済後に行えることと、SNSアプリのWeChatが本元なので、スマートにCRM施策に移行させることができる。
お店側もCRMを意識できるので、現金よりもWeChatPayの方を積極的に推奨するようになる。
まとめると、WeChatPayの凄さは、SNSの延長でサービスを拡張させ、さらに、中小企業も導入できるようにオープンプラットフォーム化し、生活者には古くからの文化をデジタルの力で利便性をあげ、お店側には決済後の顧客とのCRMに引き込むメリットを与えることで、お店側からも現金よりもWeChatPayの利用促進が行われたことにある。
華麗な全方位マーケティングで圧倒的な地位を得たのも納得できる。
日本で言うと、SNSを運用しているLINE Pay、スマホを握っているSoftBankのPayPay、今後出てくるかわからないがカード会社のPayサービスが有力ではないか。
10日で終わってしまったPayPayの100億円あげちゃうキャンペーンも、還元上限額を見直すなど、もう少し長めの還元祭を再度行い、乗り遅れて使っていないユーザーにも体験を促さないと、この火種がまた消えてしまう可能性もある。