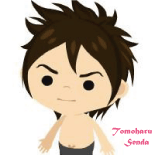多くのクライアントの主要KPIに、好意が設定されている。
インフラからエンタメ、耐久消費財、日用品まで、ほぼ全てと言っていいほど。
沢山の人に、長く愛されるブランドでありたい、というのはブランド担当者からすると当然の願い。
とくに、コモディティ化した時代に、機能差が作りづらくなっているので、情緒での差がメインの戦いどころとなる。
結果、心の結びつきに繋がっているかと、主要KPIに好意を定めることになる。
で、好意を全社的に上げていこう、それは間違いのないものだと、多くの関係者が信じて突き進むことになる。
ベストセラーとなった某戦略系の書籍に、プレファレンス(好意度)を上げることが大切と書かれていたことも後押しになっている気もしている。
ある、ブランドの例。
好意を上げようと10数年前から全社的に取り組み、毎年沢山のコミュニケーションを展開。
他社に比べて、好意が上がっているか、継続的にトラッキングしていた。
あるとき、気づく人が出てきた。
「好意が上がっても、売り上げは上がっていないじゃないか!」
好意はゆるやかに、でも着実に上がってきたが、売り上げはずっと横ばいだった。
また、あるブランドの例。
自社製品と類似した機能の製品が毎年出てきて、機能が劣勢になってきた。
もう、打ち手がないので、好意をとりに行こうと。
数年かけて、好意をあげるコミュニケーションを展開してきた。
ゆっくりとだが好意はあがってきたが、売上との関係は低く、好意よりも共感の方が関係が高いことがわかり、主要KPIを共感に切り替えることになった。
カテゴリー特性から、「好き(好意)」よりも「いいね(共感)」の方が、確かにあっていた。
最後に、あるブランドの例。
数年前から、主要KPIを最も好きという、好意の中でも一番好きという尺度を入れて追いかけることになった。
後発のブランドであり、トップ企業とのシェア差が大きく、ただの好きではなく、一番好きという強い好意がなければ選ばれないと判断。
結果、その指標が売上と強い関係があったことから、信じられる指標となり、関係者はそこを常に見ながらコミュニケーションをすることになった。
とはいっても、このブランドは、なかなか最も好きという指標が上がらなくて、苦戦しているのだけど。
言えることは、カテゴリーやブランドの立ち位置によって、好意があてはまることもあれば、そうでないこともあるということ。
また、好意が本当に売上に繋がっているか、どこかで立ち止まって確認する必要がある。
好意が信じられる指標だとしたとき、何をしたら好意を上げられるか、これまた難しい問いが発生する。