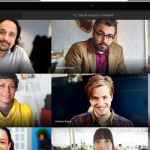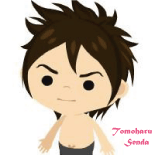成功・失敗体験をマーケターが一方的に話したり、マーケター数人で登壇し議論し合うセミナーのスタイルが定番だが、最近は、聴講者の思考にそって、架空のケーススタディを時系列で解いていくスタイルのセミナーもちょこちょこ見受けられる。
先月、日経クロストレンドEXPO2018で、「マーケティングの達人」というトークセッションで、その場で課題解決をしていくLIVE Planning(ライブ・プランニング)が行われ、その内容が示唆に富んでいた。
ヤッホーブルーイングのマーケティングディレクター稲垣さんが、人気クラフトビール「よなよなエール」の課題や目標をオリエンし、マーケティングの達人である、イトーヨーカ堂の営業本部長 富永さんと、エステーの執行役エグゼクティブ・クリエイティブディレクターの鹿毛さんが、その場でプランニングしていくのだが、思考プロセスをそのままたどって学べるのは意外と少ない。
広告会社のプランナーのプランニングの学び方は大きく2つあって、1つはOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)、もう1つは最終的なアウトプット(企画書)をもらって学ぶものだ。
販促会議の誌面連載「これがプロの企画書だ!」など、雑誌やネットで紹介されている事例は後者の最終的なアウトプットの類に含まれる。
前者のOJTで学ぶというのも、若いうちは優秀な先輩にひっついて学べるのでとても勉強になるのだが、いかんせん若手は知識が少ないので、どういう思考回路をたどったかという大事な所はあまり理解せず若手期間が終わってしまい、気付けば荒野に投げ出され一人で戦っていくことになる。
他社で実績のある方の思考プロセスをたどることで、視点の持ち方や課題の解き方が学べるのは良い。
冒頭15分前後、クラフトビールの市場概況やヤッホーブルーイングの課題が説明された。
国内ビール類の推定市場規模が約2兆円に対して、アサヒ、キリン、サントリー、サッポロのガリバー4社の売上で98%の市場を占めている。
残り2%のうち、1%がオリオンビール、残り1%をクラフトビール300社で成り立っている。
クラフトビールは人気だが、売上規模でいうとまだ1%の中での戦いだということがわかる。
そして、よなよなエールの課題は、オリオンビールと同じくシェア1%まで売り上げを拡大すること。
クラフトビールの問題点は、認知率がまだ4割ほどで、クラフトビール飲用頻度は月に1回以上飲む人が約2割と限定的。
熱狂的なクラフトビールファンが市場を支えている状況だ。
尚、ヤッホーブルーイングの製品別売上シェアは、よなよなエールが50%、インドの青鬼と水曜日のネコを合わせて30%、残り20%がその他合算という構成。
よなよなエールの、アイディアルターゲットは40歳前後のビール好き男性、マーケティングターゲットは30代男女、1ヵ月以内の自宅飲用人数は35万人。
インドの青鬼の、アイディアルターゲットは40歳前後のビール好き男性、マーケティングターゲットはクラフトビール好き、1ヵ月以内の自宅飲用人数は16万人。
水曜日のネコの、アイディアルターゲットは30歳前後のビールを飲む働く女性、マーケティングターゲットは30-50代ビール好き女性と20-30代男性、1ヵ月以内の自宅飲用人数は22万人という状況。
オリエンはここまで。
最初に、マーケティング達人は、課題を疑うことから始める。
売上シェア1%を狙う意味があるのか、ヤッホーブルーイングは、今何に困っていて、これから何を達成したいのかを質問していく。
ガリバー4社で構成される生活者のビールイメージを変えたいだったり、選択肢を増やして楽しいビール市場を創りたいということを引き出していく。
市場シェア1%を課題に設定するのではなく、生活者のビールのイメージを変えるということが課題ではないかと議論が進む。
広告会社で行う「オリエン返し」。
呈示された課題が間違っていることが大手企業でも結構あり、よくよく話を聞くと別の課題を解決することがブランドにとって良い事だったりする。
課題の設定がすべての始まりで、最も大事な事なので、オリエンをそのまま鵜呑みにせず、根っこの解決したい課題を改めてセットし直し、そこを解いていこうとしている。
次に行ったのが、コトバの定義を改めて行い、関係者間の意識のズレを無くした。
まだクラフトビールやヤッホーブルーイングの認知が限定的という問題に対して、「認知」とは何か、どういう状況になっていると、その「認知」が得られたと定義しているのかを確認する。
よくよく聞くと、ただブランド名を知っているだけを認知と呼んでなく、ヤッホーブルーイングでは、便益まで理解している状況を認知と定義していることが分かった。
つまり、理解浸透が達成しなくてはならないゴールであり、ただSNSでブランド名を連呼するようなプロモーションは求めていないことがコトバの定義からわかった。
ちなみに理解寄りの認知に関してのアプローチは、ヤッホーブルーイングを知っている人に刺激を与え、そこからブランドを知らない人に伝えるファンベースのマーケティングアプローチもあるし、まだ未開拓で認知が十分でない層へ広告で直接アプローチする手段も有る。
ユーザーピラミッドでトップダウン型でいくかボトムアップ型でいくかは時間の関係上そこまで議論せず次の検討時効に移る。
次に行ったのが、ターゲットの定義。
今のヤッホーブルーイングのお客様構造を、熱狂的ファン(伝道師)、ファン、好意的リピート、再認~トライアル~リピート、認知、非認知の6段階に分けたり、ヤッホーブルーイングのクラフトビールを週1回以上飲んでいる人にするのかを議論。
結論は、クラフトビール認知者をターゲットに設定。
その次に行ったのが、ターゲットのインサイト発掘。
ここで大事だなと思ったのが、n=1を大事にしたアプローチをしていたところ。
会場にいるお客さんの中で、週1回よなよなエールを飲んでいる人を壇上にあげさせ、簡易デプスインタビューが始まった。
普段のビール飲用状況や、よなよなエールの飲用状況、その違いなどを細かくヒアリングをしていく。
その人は、キリンやサッポロの(ふつうの)ビールを毎日、食事と共にお茶変わりにグビグビ飲む。
一方で、よなよなエールは週1回、チビチビ味わいながら飲む。
その後、ビールとは何か、何故人はビールを飲むのか、その中で、よなよなエール(ヤッホーブルーイング)とは何かというところをヒアリングを通じて仮説を立てていく。
その人にとって、ビールはお茶のように飲むものであり、飲んでいるときの自分は「猿」と定義。
よなよなエールは、ゆっくり味わいを楽しみながら飲むものであり、飲んでいるときの自分は「人間」と定義している。
マクロの視点とミクロの視点を行ったり来たりして、生活者から見えるカテゴリの定義、ブランドの定義を言語化していく。
その次に行ったのが、ベネフィットの整理。
機能ベネフィットと情緒ベネフィットが何なのかを商品起点で分解していく。
マーケティングの達人の富永さんは、ワイン事業部にいたこともあり、お酒にはかなり詳しく、よなよなエールの機能ベネフィットを、ポップの苦さ、フルーツの香りがしっかりしていると定義し、情緒ベネフィットをデザインのセンス感、エッジ感があると定義。
通常の飲み会では、ビールが議題になることはなく基本は会話が主役だが、ヤッホーブルーイングのビールは、ビール自体が議題にあげられ、その香りや味わい、パッケージが飲み会の主役となり得ることを指摘。
ここからは、コアアイデアを出し、施策へと落とし込んでいく。
※ちなみにマスを行うほどの施策予算が無いというのを前提に
数十分の講演の中でオリエンから提案まで行うので、正直大きなアイデアジャンプはできていない感はあるが、分析から施策へ落とし込んでいく。
マーケティングの達人が目を付けたのは、よなよなエールの特徴的な缶のデザイン。
よなよなエールのアートワークをゲリラ的に色々な所で貼っていき、ファッショナブルでお洒落な印象を若者がいる街を中心にブランドの世界観でジャックするというアイデアや、水曜日のネコは飲みやすいため、エントリービールとして位置づけ、水曜日のネコ→よなよなエール→インドの青鬼という順にヤッホーブルーイングのロイヤル化をはかるというアイデアを出し、講演はフィニッシュした。
ここで言えることは、施策のストーリー仮説は、サイエンスと妄想の組み合わせで作られるということ。
デプスインタビューや定量調査をたくさんやり、生活者を知ることはとても大切だが、どこまで行っても生活者がすべての答えを出してくれるわけではない。
調査ではわからないことがどうしてもある。
普段人は何かをやるときは定型的に決まっており(無意識の行動が大半で)、行動した理由が曖昧なためだ。
その時に必要なのが、妄想力。
ビールを飲むってどういうことか。
きっと、よなよなエールを飲むときは、もう一人の自分に出会うためではないか、仕事の仮面を脱ぎ捨てて自分の理想を目指すために、よなよなエールを飲むのではないか。
よなよなエールは、頑張る自分をエンパワーしてくれ、明日を頑張るためのスイッチである。
ビールを飲むときはお風呂に入っているときの気持ちと一緒で、飲んだ後の「ふぅ~」は日本の文化であり、「明日もがんばるぞ!」と思うために、人はビールを飲む。
そんなターゲットには、明日を頑張るスイッチを想起するイベントを中心としたプロモーションが適していそうだとサイエンスと妄想を組み合わせてストーリー仮説を立てていく。
後半は妄想全開なんだけど、この行ったり来たりが大事。
講演で印象的だったのが、マーケティングの達人が糸井重里さんと一緒に仕事にしたときの話。
「糸井重里さんとお仕事をしていたとき、彼が『それって大和時代の人が喜ぶのかな』と指摘したときがあり、人の根底にあるインサイトは時代が変わっても変わらないものだと気付かされた」と言っていた。
時代が変わっても不変のインサイトに、今の世の中の時代の流れや、カテゴリの置かれた状況を考慮した視野というかスパイスを振りかけ、プロモーションを設計していくのは、他の企業でも、他のマーケターでも同じということが分かった。