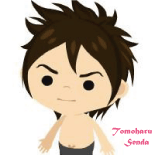今年のセミナーや講演会、フォーラムのメイントピックスは間違いなく「顧客体験(CX)」で、多くの企業が「CX」と名のつく部署を立ち上げたり、名称を変えている。
ブランド視点から顧客視点に変えようよ、というメッセージを色々な人が事例と共に語っている。
物や機能で差がつきづらいなら、顧客とブランドとの距離の近さで勝負しようと、共感、寄り添い、驚きみたいな指標を重視している。
顧客体験の役割を、顧客とブランドとの距離を近くすることと定義してもよさそうだ。
少し前に、「デジタルとは何ぞや」とデジタルの役割が議論されてきたとき、デジタルとは顧客とブランドとの距離を近くするもの、という考えが広がったが、最近はマスもデジタルもリアルもすべての接点が、それらを担うのは当然だよね、というところにシフトしている。
まだまだ、企業は顧客のことをきちんと理解していなくて、誰が自分たちの商品を買っているかをわかっていないことも多い。
ガシガシ売れているブランドであっても、ブランド担当者に「あなたの商品はどんな人が使ってますか?」というと、モゴモゴ答えられないこともいまだにある。
自社商品の愛用者、他社商品の愛用者を呼べで数回、グループインタビューを行えば、だいたい自分の商品がどんな人に買われているかがわかったりする。
例えば、ドコモやソフトバンクといったオールターゲットなサービスであっても、「ドコモを愛してやまない人たち」に共通した像がみえるはずだ。
それは、デモグラではなく、共通した意識価値観で、把握しておくべき。
また、最近の傾向として、定量・定性調査を膨大に時間をかけてやるよりも、ソーシャルリスニングで代替せよ、みたいな流れもあるのだが、それは結構危なかったりする。
ソーシャルの良いところはスピードであって、リアルタイムに顧客の声を集めることができ、what(何を語っているか)はわかるが、一番大事なwhy(何故そう語っているか)やwho(誰がそれを語っているか)が分からない。
whatでキザシを見つけられても、whyやwhoまでたどり着いて考察しなければ、深い顧客体験を実現することは難しい。
それに、ソーシャルで語られている感情は、可愛い、キレイ、面白い、好きといった、シンプルな感情しかなく、深く複雑な感情まではソーシャルで把握することには限界がある。
やっぱり、泥臭く、愛用者に直接会って短い時間でも話を聞くのが一番大切だ。
顧客を知ることは最低限のステップとして、その後、ブランドがどのように顧客との距離感を詰めていくかを検討しなくてはならない。
顧客体験の傾向は、大きく4つに分けられそうだ。
不満削減・利便性向上
「ずっと面倒だったが、こうだったらいいのに」といったストレスを解放することで、顧客とブランドの距離を縮める顧客体験。
ディズニーランドが7月に出した「東京ディズニーリゾート・アプリ」はわかりやすいもので、アトラクションの待ち時間を地図で可視化したり、ショーの予約をアプリからできる。
一番嬉しいのが、ディズニーランド独自の買い物がアプリでできることだ。
ディズニーランドはとにかく疲れる。乗り物も、レストランも、買い物もどこに行っても並ぶ。
何をしても疲れてしまうくらいストレスがかかる中で、パーク内のすべてのグッズがスマホで決済ができ、店頭でピックアップしたり、配送もできる。
「ECと一緒じゃん」と思いがちだが、パークに来ることで買い物ボタンが押せるようになっており、ここでしか買えないグッズがスマホで買えるという、ディズニーならではの顧客体験が設計されている。
不満削減という視点で言うと、airClosetもその類のサービスであり、買い物に行く時間のない働く20-40代女性が主に使っている。
自分で試着する時間がない、いつも同じような色を選んでしまう女性に対して、定額でスタイリストがレコメンドして届けてくれる。
利便性という視点で言うと、folioもそうだ。
証券を買うとなると、専門的な知識が必要だったり、最低購入価格がハードルとなるが、「テーマ投資」という右脳的な買い物ができるようになっている。
「VR」「人工知能」「京都」といったテーマで証券を購入でき、あまり知識のない一般の人でも、カテゴリという異なる軸でくくられることで購入ハードルを下げる体験が設計されている。
心の寄り添い
無機質なデジタルの中に人の温かみを感じさせることで、顧客とブランドとの距離を縮める顧客体験。
リアルの体験をデジタルに持ってくる、二次元の行動を三次元に持ってくることで実現される。
一回行っただけのお店なのに、自分のことを覚えてくれていたり、「○○さん、お久しぶりです」と、名前で呼んでくれたりするとお店に対して愛着を持ちやすい。
美容院や飲食店では、会話した内容をこまかくメモにして、次回のサービスに活かすということは良くある話だ。
アメリカのスターバックスでは、名前を呼んでくれるだけでなく、カップに名前も書いてくれるので、他の珈琲ショップよりも親近感を持つ。
ECでは、「○○様マイページ」など、当たり前のように名前が書かれているが、それをリアルのサービスで実現するだけで、自分のことを理解してくれている感じがするのが不思議。
ちょっと前の事例だとザッポスもその類に入る。
顧客の課題解決の為なら何時間でも一緒になって電話口で相談に乗ってくれるし、たとえ顧客がザッポスのお店で買わないことが分かっていても、最寄りの競合のお店を知らせてくれるなど、お客様視点で行動してくれると、顧客は寄り添いの見返りに愛着を覚える。
究極は、コンシェルジュというサービスに行きつく。
いつでも顧客のそばに寄り添い、顧客の望む課題に対して、全力で向き合ってくれる姿勢こそが、最高の顧客体験を生む。
特別なおもてなし
濃いファンに対する特別な体験を提供することで、より顧客とブランドの距離を近づけ、さらなる熱狂度を高めるものを指す。
デルアンバサダー、Xperiaアンバサダー、ネスカフェアンバサダーなどのアンバサダー施策が分かりやすい。
濃いファン同士の集いを提供したり、ファンと従業員との接点を設けることで、より良いサービスの提供に繋げていく意味がある。
CDをたくさん買った人が長時間握手できる「AKB握手会」もそうだし、広島東洋カープの野球を見ながらBBQができる「びっくりテラス」も同じようなものだ。
企業が特別なおもてなしをすることで、顧客は満足度を高め、その対価にお金を多く落とす。
未体験
いままで見たことのないような体験をすることで、その衝撃と共にブランドに対して顧客は驚きと好意を持つ。
最近勢いのあるチームラボがわかりやすい。
チームラボボーダレスの動く芸術は、老若男女、また、国境を越えて驚きと感動を与えることができる。
新しい花火イベントのSTAR ISLANDもそうで、花火と連動して光るブレスレットや、光と音をミックスさせた3Dサウンド、寝そべって見れるベッド席など、これまでなかった花火体験を提供することで、顧客もその価値に対して数万円の席料を支払っている。
スポーツ領域も、この顧客体験を向上させようとしており、フェンシングの太田雄貴も、スポーツイベントのエンターテイメント化を目指して、LEDを使った光の演出や、選手がポイントを決めた時はリプレイでビジュアライズドするなどして、これまでにない顧客体験を提供することで、観客数を大きく伸ばしている。
総じて、モノよりもサービスを提供している企業が顧客体験の向上に取り組んでいる。
サービスは人にアプローチすることができるため、サービスの向上は顧客体験の向上に直接つながる。
モノを販売するメーカーも、付加価値であるサービスを身にまとうことで、顧客体験の向上に取り組んでいる。
ライオンのハンドソープIoTのPush Connectionの提供や、ロレアルのModiFace買収によるリアルやデジタルでのメイクアップの体験向上がその例だ。
また、顧客体験に必要な視点として「期待値(エクスペクテーション)」も大事だったりする。
ターゲットの期待値をきちんと理解し、どのくらい期待値を超えてモノやサービスを提供するかを設計することが大事という考え方。
期待値をどのように計測し、それをどう超えるようにブランドが設計するかが顧客体験には求められる。
今後も、顧客体験に関する議論が増えていくと思われるが、マーケターも顧客起点のプロモーション設計をすべきだと改めて思う。