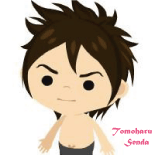「幻冬舎と言えば見城徹」と言うくらい、有名な社長がいる。
その見城徹社長のアツ過ぎる生き方や強烈な人物像が好きで、彼の書籍を片っ端から購入している。
個人的に好きなハードボイルド作家の北方謙三にどことなく似ているというか荒っぽい所や、男臭い所、自分をしっかり持っているところがあるためか。
で、彼の書籍を読みふけっているときに思っていたのだが、強いアイコン的な社長がいる企業ってその人に匹敵する後継者がなかなか現れないなと。
見城徹のいなくなった幻冬舎ってどうなるんだろと。(まったくもって余計なお世話だけど)
他にも、ソフトバンク、ユニクロ、楽天、ZOZO、サイバーエージェント、…など、社長が企業の看板にもなり、社長がひっぱっている会社も少なくない。
そんなことを考えていた数年後、あの強烈な見城徹社長と同じかそれ以上の勢いのある社員が幻冬舎から現れた。
箕輪厚介さん。
今や飛ぶ鳥を落とす勢いの編集者。
この人の行動、発言、イマドキっぽくて、お世辞抜きにカッコいいなと。
なんかホリエモンが出てきた時くらいの衝撃を、個人的には受けた。
そして気になって常に目(ネット)で追いかけてしまう。
肩書。
「幻冬舎・編集者」
「NewsPicks Book・編集長」
「堀江サロン教授」
「合同会社波の上商店を設立」
「CAMPFIREと幻冬舎の共同出資会社、エクソダス取締役」
「月額6千円のオンラインサロンで1300人以上のメンバーを集めている」
手がけた書籍も常にヒット連発。
『ネオヒルズジャパン』与沢翼
『たった一人の熱狂』見城徹
『多動力』堀江貴文
『人生の勝算』前田 裕二
『己を、奮い立たせる言葉。』岸 勇希
『お金2.0 新しい経済のルールと生き方』佐藤 航陽
箕輪さんを知らずに全部買ってたわ。
見城徹社長も絶賛。
”編集者の天才”
箕輪は、【極端】で【明快】で【オリジナリティ】があって、そして【癒着】する天性の才能を持っている。
すなわち、僕がいつも言っているベストセラーを作る4条件をすべて備えている。
だから僕は、箕輪が熱狂するものは、僕がワケが分からなくても、必ずヒットすると信じている。
僕以来、久しぶりに出てきた、編集者の天才だ。(波の上商店より)
ネットでもすごい声が。
「売り方まで編集できる編集者」
「ホリエモンが絶賛する箕輪厚介の仕事ぶり」
「今もっともヒットを生み出す編集者」
「ホリエモンだけでなく、格闘家の青木真也やブロガーのイケダハヤト、さらには研究者の落合陽一などからも箕輪厚介の才能は絶賛されています」
サンジャポで「今売れてる本はだいたい僕が作っている」と豪語したり、
自己ブランディングがうまく、ビジネス・ビッグマウスもうまく使いこなして興味をそそる。
彼の記事について、広告会社のプランナー視点で示唆がある発言をとりあげてみる。
雑誌広告ってほぼやることないんですよ。電通に行く必要もないのに行って、電通の人もなんでわざわざ打合せしなきゃいけないんだと思ってるような。
雑誌持っていって、媒体資料見せて、「表4空いてるんですけど何かないですかね?」と聞くんです。5、6年前で出版がまだギリのときだから、広告くださいと言ったらそれだけで何かしら広告をもらえた最後の時期でした。
そういう感じでやってたけど、暇でやることなくて、何かないかなと思ってたときに与沢翼という、あの秒速で1億円稼ぐ男がいきなり出てきて。札束を積み上げながら時計を買ったり、ヘリコプター乗ったりしているのを見て、雑誌の反響に関係なく、ありとあらゆる手段で、むしろ雑誌が世の中に1冊も出てなくてもいいぐらいの感じで広告を強引に取っていたなかで与沢翼を見たから、「来た!」と思って。こいつだ、俺がずっと探してた奴だと。「こいつから金取れる」って思ったんですよ。
それですぐに会いに行ったら、雑誌をつくりたいって言うんです。僕は相場がわからなかったけど「3千万あればつくれます」と言ったら、与沢が「いいですね」って。それで3千万もらってつくることになって、そのとき会社は現金がないと言っていたから意気揚々と帰ったら、「お前そんな怪しい金を持ってくんな」と言われて。ダメって言われて。マジかよと思って。
社長賞をイメージしていたら、「お前そんな詐欺師みたいな金持ってきちゃダメだろと。でも、そのときはお金よりも与沢という人間に興味があって。嘘っぽいけど、テレビにガンガン出まくってる人独特の、時代の寵児のオーラってあるじゃないですか。
与沢にはそれがあったんですね。ロールスロイス乗って、上の屋根がプラネタリウムみたいになってて。お風呂付きの西麻布の焼肉屋で金粉まぶした焼肉を食べたり。そういう人だったんです。それ自体が楽しくて本を出したいと思ったから、社長を死ぬほど説得して、「お前がそこまで言うのならいいよ」となって。
でも編集を誰もやりたがらなかったし、編プロに投げるのはダメと言われて、結局、「揉める案件な気がするから箕輪がやれ」と言われたんです。だから雑誌『ネオヒルズ・ジャパン』のクレジットは、総合プロデューサー:箕輪、広告:箕輪と、箕輪ばっかりです。
編集もやったことなかったけどやることになって。金はあるから表紙はレスリー・キーに撮ってほしくて。そしたら会社の人たちから、「恥ずかしいからレスリーの会社に企画書を出さないでくれ」と言われて。でも、普通に電話したらいいですよとなって。
それから二転三転して、前日にレスリーが「絶対撮りたくない」と言いだしたんです。レスリーは、ユーミンなど本当に好きな対象は借金してでも写真展をやったりするらしいんですよ。その人のことを好きになってから撮ると。
でもこの件は、前日に「与沢翼」で検索してみたら、「成金」って書いてあるから、「何億円もらってもやりたくないと。僕のキャリアをこんなところで潰すのか。なんでこんな仕事を受けたんだ」と社長と喧嘩になっちゃって。そういう僕も、なんで受けたんだろう?と思ってる側だったんですけど。
とはいえさすがに前日は、と。前の打合せでレスリーが飛行機に乗り遅れて海外から帰ってこれなかったから、前日にそういう騒動になっちゃって。だからとりあえず現場に来てもらって、僕が説得して無理だったら、もう事務所の他の人でいいですと言ったんです。
でもレスリーはいい人だから。写真撮って逮捕されたりしてたじゃないですか。そのぐらい善悪じゃなくて、写真が好きでしょと。だから、「与沢も善悪じゃなくて、お金が好きなんだ」と説得して。
「アスリートが1秒を縮めるように、与沢は1万円を積み上げてるだけなんだ」と。そう言ったら、「わかった。怪しいけど時代を切り取るということでやろう」となって、そこからグルーヴしていって、それこそ筧美和子さんも出てくれて。全てが「なんで受けちゃったんだろう?」という連鎖が起きたんです。
僕が本当に未経験で常識を知らなかったからだと思うんですけど、ミイラ取りがミイラになるじゃないですけど、最初はみんなバカにしてたのが、どんどん自分事になって、『ネオヒルズ・ジャパン』は面白いとなって。
それで、発売日に与沢が書類送検されて。ネットニュースで「与沢翼責任編集長の雑誌、創刊日に逮捕、廃刊」って。これがバズかと思いましたね。アマゾンランキング1位になって、すぐ完売して。僕は社長から「絶対何もないよな?」と念を押されて出したから、怖くて会社に行けなかったんですよ。
それでずっと会社の近くの漫画喫茶行ってネット見ていて、どんどん事が大きくなって、これはやばいと。電話も鳴りやまなかったけど、上司から「社長から聞かれる前にお前から行かないと本当に回収になるから、仕掛けたと言え」と言われて。
いや、さすがに「書類送検を仕掛けた」って通じないだろと思ったけど、もうどうでもいいぐらいの気持ちで、「ネットで仕掛けてるんです。だからニュースが出ても想定の範囲内なので心配しないでください」と言ったら、社長はそういうの疎いのかわからないけど、「お前すげーな」と。それでOKになって、3万部つくって完売したんですよね。
(すぐおわアドタイ出張所より)
与沢翼がもっと売れると踏んだ「嗅覚」と、何が何でもやりたいことを通す「熱量」。
この二つが秀でているなと。
総合代理店になると、色々な人がいるので、色々なものに張っている。
ヒットするものもあれば大ゴケするものもある。
セカンドライフやPinterestの大ゴケもいい例で。
その中でも嗅覚・目利き力は大切な能力だ。
時代の流れを捉えて、次に来るものを確実に見つける。
更に、広告会社で特に必要なのは「熱量」なのかなと。
人が多い分、意見が上から横から斜めから飛んでくるが、あれこれ言っても最後「熱量」の多い人の意見に乗る。
「どうしてもこのアイデアを入れるべきだ」
「このストラテジーでないと市場では絶対勝てない」
「このプロジェクトを絶対立ち上げたい」など。
広告会社なんて、見えない未来のプランニングが殆どなので、強い想いや周りを巻き込むアツい情熱がみんなの拠り所になる。
僕が岸さんのようなザ・プロフェッショナルの人達で好きなのは、彼らは暇じゃないから、期限を決められてモチベートされるとやり切ろうとやってくれるんですよね。
作家はそうあるべきじゃないと思うし、どんどん自分を掘っちゃって迷子になって出て来ないみたいなことがあるけど、ビジネスマンや起業家はそこまででできることをやり切ろうという人が多いから。
ぐだぐだと1、2年かけるやり方もあるけど、僕の今のやり方は2、3か月でつくらせちゃう。それこそメタップス佐藤さんの『お金2.0』のような、仮想通貨やVALUがワーッと盛り上がった瞬間に決定的な本が出るのがいい。
だいたいああいうのって、VALUやタイムバンクがワーッとなった瞬間につくりはじめて、やっと今ぐらいになっていろいろな仮想通貨の本が出る。ホリエモンの本(『これからを稼ごう 仮想通貨と未来のお金の話』)も、間もなく出るぐらいなんです。
今の時代の流れからすると遅すぎるんですよね。
(すぐおわアドタイ出張所より)
意外とこの生活者のタイムラインに合わせて打ち手を出していくのって、簡単じゃない。
企画立案→提案→承認→制作→確認→修正→実施という正規の手順を踏むと、コンテンツ作りだけで頑張っても数日かかってしまうし、広告配信まで入ってしまうと、入稿や考査もあるので更に時間を要する。
広告を出稿するころには既に生活者の盛り上がりが終わっているなんてよくある。
IT業界を中心に、アジャイル型の組織とか、スクラム型の組織という体制について議論されることが多いが、その根源は、市場の早いサイクルに対応するための組織作りだ。
広告主側にもそういった組織が外資を中心に徐々に出始めているが、ワーッと盛り上がった瞬間にオウンドや自社SNSアカウントで打ち手を次々と出していくのをまだトライしている状況だ。
作った書籍の告知について。
全部やってますね。ただ、そんなに分離して考えてないというか、本の中身も新聞広告を意識しながらつくるし。最近、「はじめに」を無料で公開することがよくあるじゃないですか。それがバズってアマゾンで1位になったり。
だから当然、「はじめに」をつくるときも無料公開を意識してるし、宣伝とコンテンツと分けてないので、物理的に忙しくても全部やらないといけないから、僕はネットまで追いつかないという発想はないですね。全部がいっしょくたなんで。
(すぐおわアドタイ出張所より)
どこもかしこもトータルプランニングの重要性。
分断しているプランニングでうまくいったものはない。
「はじめに」を無料公開して、SNSでバズらせてアマゾン1位を取るなど、時系列を意識したシナリオプランニングも大事だと。
最近、デジタルを使ったコミュニケーションでは、「プレバズ」が増えてきた。
マクドナルドがその指標で販売前のクチコミ最大化を狙っていたが、他の企業も効果を理解し、マスト施策としてきた感があるな。
広告業界でも、出版業界でもやるべきことは同じということか。
自信が保有するオンラインサロンのコミュニティについて。
コミュニティは定義を定義するみたいな時期なので難しいんですけど、一種の価値観、こういうのが好きだよねという共通項において、ネット上で同じ価値観において繋がっている集団という感じですかね。
ツイッターのフォロワーという、緩いけど広い100万人ぐらいのコミュニティから、ホリエモンに月1万円払うことで秘密のFacebookグループに入れて、ホリエモンと直でディスカッションしながら一緒に仕事を進めていく2千人の濃いコミュニティまで、いろいろ段階があります。僕がホリエモンの『多動力』をつくる際に巻き込んだのはオンラインサロンの2千人のうちの100人ぐらいですね。
広告もそうかもしれませんが、出版は本当に顕著で、エゴサーチをしてるとミリオンを出した堅いレガシーな編集者は「コミュニティと言ってクオリティをごまかすのはダメだと思う」と。僕の名前を出してないけど、確実に僕に向けて言ってるなと。
当然その気持ちはすごくわかります。世の中に初めて出して判断されるという通常の流れをコミュニティでごまかしてるじゃないけど、「仲間内に売って、それで盛り上がって現象をつくっちゃうのってズルくない?」という気持ちは想像できなくはないですね。
ホリエモンはネット上に緩やかにコミュニティを持っていて、それこそオンラインサロンが2千人ぐらいいて、フォロワーが100万人ぐらいいます。ホリエモンって毎月のように本を出していて、コミュニティ自体はホリエモンの本に飽きてるんだけど、そこの人たちを巻き込んで一緒につくったり、宣伝したりすることで、コミュニティの中でも「特別な本だよね」という位置づけを『多動力』ではしていて。
そうすると火のつき方が違いますよね。当然、内容とリンクしてくるから、単純にノウハウ論でやってもうまくいかないんですけど、自分事にしていくというか。まず本ができる前に校閲などをサロンメンバーにさせてましたね。
ゲラができあがった状態で中身をちょい出しして見せて、校閲してくれた人のクレジットを本の中に入れて。ゲラは普通の人はもらったりしないので、スタッフになった感が多少あったと思うんです。「これツイッターにアップしていいんですか?」と聞かれて、「どんどんアップして」と。もう発売前にざわざわしていた感じですね。
昔の雑誌に近いのかもしれないんですけど、同じ価値観、あるあるネタが通じるぐらいの同じノリが通じる人たちの集団で、密室的にモノをつくって、ここだけで通じる内輪ノリがあって、それが本の発売日になって書店に並ぶと、彼らにとってはそれが売れることが一番面白いから、文化祭のノリで宣伝したりして。
そうすると、これだけモノが溢れてどれを買っていいかわからない一般の人にとっても、熱が乗ってる本だな、よく聞くなというものになっていて。内輪的な集団において熱狂が伝播していく感じなんですよね。
いろいろな観点においてあるんですけど、まずお金を払うことでフィルターになっているというのが1個あって。僕のオンラインサロンは月5800円で千人ぐらいの集団で、今度ニューズピックスブックの1周年フェアの書店フェアをやるんですけど、その全デザインはうちのサロンのデザインチームがやったんですよ。
企業に発注したら50万ぐらいかかるし、幻冬舎内のデザインの部署に頼んだら「そんな時間じゃつくれない」と断られて。じゃあ、僕のところでやろうと投げて。彼らは僕にお金を払って、寝る間も惜しんでデザインをつくるんですよ。クオリティも高いので、最高な組織なんですけど、お金を払っていることがモチベーションの最初のスクリーニングになっているんです。
炎上させようという悪意がある奴、悪意はないけど興味があるから覗いてみようという緩い奴がいないから、一種の熱狂空間になるんですよね。普通の会社って、どんな頑張っても月給ってそんなに変わらないじゃないですか。
月給30万として30万で仕事してると、仕事が増えると損した、なんで給料が変わらないのに仕事だけ増えたんだと思ったりするけど、オンラインサロンは逆に払ってるから、むしろ仕事がエンタメというか、僕が「これやって」と言ったら、みんな飛び込んでくるんですよね。それやりたいって。
デザインのように、こだわればこだわるほど良くなる余地のあるものって、やらされてる感がある人と仕事をするより、「気づいたら徹夜しちゃってました」という人と仕事するほうが楽しいし、文化祭みたいになっていくんですよね。
それを会社でやると法律に引っかかるけど、サロンはサービスとして働いているからモチベーションが100%の状態です。給料をもらってたらやる気なくてもローンや家族のために辞めないけど、サロンはお金を払ってるからやる気がなかったら辞めるので。だから淀みがないですね。
オンラインサロンの黎明期はおままごとみたいな感じで、「あいつらはちゃんとしたものを出せない」となってたんですけど、今はうちだったら任天堂にいたデザイナー、ライターもプロのライターが入ってるから、大丈夫ですね。
(すぐおわアドタイ出張所より)
ZOZOの田端さんが「ブランド人になれ! 会社の奴隷解放宣言」という書籍を出しているが、今後サラリーマンをやりながら、外部へ情報発信し、新たに仕事を生むプロサラリーマンのような存在が増えるのかな。
電通を辞めた、はあちゅうもその先駆けだった。
個に集まるファンをモチベートさせて「共創」する。
あと、大事な視点として巻き込むことで「共犯者」にするというのもある。
会社でもあれこれうるさそうな上司がいたら、先に会話をしにいく。
提案ではなく、あくまで相談として。
人は相談されたら、親身になって助言をする。
そして、助言をした人間は味方になる。
後からそれを否定するのではなく、それを擁護する立場へと変わる。
一緒に作った商品は、ファンにとって愛着があるので、人に伝えるし、継続して使ってくれる。
販売前に情報共有することで、ファンは他の人よりも優越感を感じ、その作品を世の中でヒットさせたいと自分ごと化してくれる。
AKBのファンが推しメンを育てるように、ファンと一緒に商品を作っていくのもこれからの手だ。
どんな人と書籍を作りたいかについて。
水と油のように、世間と個人の原石をどんなにかき混ぜても分離しちゃうような人ですね。それこそ与沢翼も前田裕二も岸勇希さんも、いい悪いはいったん置いておいて、確実に分離しちゃう。その分離の仕方が僕の好きな分離の仕方という感じですね。
青木真也という格闘家の本もつくったんですけど、彼は格闘技界から嫌われていて。倒れて負けて骨が折れている相手の顔に中指立てて騒いで問題になるような、本当に単なる問題児なんですけど、僕はそういうさまが好きなので。
でも最初は彼の異常性ってコンテンツとして一般性がないなぁと思ったんです。格闘技ブームでもないし本にならないなと思っていたけど、うちの妻がママ友と行きたくもないランチに行かなきゃいけなくて面倒くさい、送り迎えのときもバスの停留所に僕が子どもを連れていこうとすると、恥ずかしいから行かないでと言うんです。
空気読みまくりで面倒くせーなと。一方、青木さんは友達できたことない、小学校のとき壁に向かって給食を食べさせられていたなど、空気なんて読んだことないし、空気という存在すら知らないと。だったら空気を読みがちな人たちに向けて青木真也を一般化すれば、売れるか売れないかわからないけど時代にピッタリの本になるんじゃないかなと思って。
それで『空気を読んではいけない』という本を出して、3、4万部ぐらい売れたんですよ。
デジタルコンテンツにしないのは特に意識してなくて。単純に編集者だから今は紙の本をつくってるだけで、それこそオンラインサロンだったらnoteで出したり、動画やったり、いろいろやってるから、単純にそこが軸足というだけなんですけど。
本の強さというのは全く変わってないし、むしろ本を読むのが日常的じゃない世代、それこそ僕のつくってるニューズピックスブックのメインユーザーである30代以下の世代は、むしろ斜陽産業になってしまったがゆえに、本が非日常のアイテムになってる気がしますね。
今はWeb記事がありすぎて、それがバズっても明日誰も覚えてない。でも、上の世代と比べて「本なんて買わねーよ」という世代だからこそ、面白い本があったら本を買うという行為自体がエンタメになっていて。そこは強みな気はします。
紙の本がなかったらこんなに話題になってなくて、ニューズピックスブックはファッションアイテムに近いですね。それこそ落合陽一さん、前田裕二さんは普通にツイッターにいて、リツイートしてくれたり、反応してくれたりする。本は言論空間というか、若い人たちが熱狂する空間へのチケットみたいなものですね。
だから、僕のつくる本は書店の棚でいくとダイヤモンド社、日経BPの本と並べられるけど、立ち位置が違って、読者は好きなアーティストのライブに行くなど、そっちの感覚に近いんですね。若い人達の盛り上がりに参加するための共通チケットみたいな感じです。
落合陽一さんの本を読んでない人結構いると思いますよ。でも、落合陽一のあの感じが今っぽくてかっこよくて、アーティストに憧れるように、落合陽一がかっこいいという人たちにとっては、あれがバイブルな感じなんですよね。
(すぐおわアドタイ出張所より)
水と油のような分離してしまうような個性を好むのはわかるけど、きちんと生活者の興味に着地させて書籍を出しているのがすごいなと。
空気読まない青木真也と、空気ばっかり読み続ける現代の女性に向けて書籍を出版する。
優良なコンテンツがあっても、課題を持っている人や物と結びつけるセンスは広告会社でも大切だ。
あと、デジタル時代の若年層にとって、書籍が「非日常のアイテム」であり、「熱狂する空間へのチケット」であると定義してい視点が面白い。
たしかに今の若い人はデジタルデジタルしているので、リアルなモノが逆に非日常で新鮮に感じやすい。
チェキが売れたり、チームラボのような体験型美術館が人気だったりと、「手触り感」のあるモノ・コトの方が好まれやすい。
全部見城さんに任せてもらってから、本当に他の講談社や集英社じゃ1年かかって決断するのを1日でできますね。
せっかちなんで。
あとみなさんがやってるCMの仕事もそうだと思うんですけど、突発的な何かのほうがズバッとハマるときがあるなと。
僕も双葉社のときは年に何冊も出す奴はダメだと思ってたんですよ。クオリティ低いだろう、真面目にやったら無理だろうと思ってたんですけど、今みたいにとにかく出さないといけないという状況になると、妥協するところもあったりするんだけど、それと引き換えにものすごい意図してないけどズバッと時代に合ったり、間に合わないからやってしまったことがウケたり。どっちが良い悪いじゃないですけど、時間ない中でやると思わぬ成果が出たりしますよね。
実はニューズピックスブック史上、初めてひと月飛んだんですよ。だから会員には謎の本が送られたんです。ニューズピックスの中の連載をまとめた、現代アートっぽい表紙でタイトルも何もない本を送って。
誰か怒るかなと思ったら、表紙が現代アートっぽくてかっこいい謎本だと、プレミアな感じになって(笑)。「今月、謎本が来た。会員限定だ」って。佐渡島さんは森の奥に入っちゃって、原稿来ないなとツイッターを見たら、「そもそも〆切という概念自体、常識がつくりあげたものなのかもしれない」ってつぶやきはじめて。
おー、戻ってこいと。そっち行くなと。そっち行ったら永遠に出てこれないぞと。そしたらこの本にも書いてあるけど、アップデート主義という言葉をつくりはじめて。今の時代、生半可なものを出すことによって人を巻き込んでアップデートしなければならないと、自分の中で概念を変えたんですよ。「そうそう、アップデート主義だよ」って言って(笑)。
(すぐおわアドタイ出張所より)
クオリティよりもスピードを重視するスタイルについて他の記事でも語っていた。
水道橋博士とボクシング試合が決まった時の記事について。
「即決」は一流の証し
――それでも、誘いがあったら受けるのですかノリで受ける。ビジネスでもなんでも、「一流」と「一流以外」の違いは、その場で即決するかどうか。
ホリエモンやキングコングの西野(亮廣)さん、SHOWROOMの前田(裕二)さんとかメタップスの佐藤(航陽)さん、落合陽一さんたちとLINEでやり取りをしていると、「行きたい」「やりたい」という曖昧な言葉は出ない。「行きます」「やります」なんです。もちろん都合があって「無理です」ということもあるけど、みんな基本的には面白いことには瞬間的に「行きます」「やります」と返事をします。
でも意外と、当日ドタキャンをすることがあるんですよ。僕もそうだけど、「あれ、いない」みたいな。見切り発車でもなんでも前のめりなんです。何でも誘われた時点で即断即決で手を挙げることが癖になってしまっている集団ですね。
でも、大企業に勤めた学生時代の友達とかのグループLINEでだと、返事が「行きたい」や「やりたい」なんですよね。
「えっ、どっち」ってなりますよね。
その時に気がついたけど、これは仕事においても全部同じだと思う。「行きたい」「やりたい」「人生変わりそう」という人は多いけど、やっぱりすごい人は、その瞬間に行動する。意識より先に行動がある。「行く」「やる」「人生変える」なんですよ。
――同じようにも思いますが……
すごい単純なことだけど、どういう習慣で生きているかで、人生は本当に大きく変わります。だから僕は、口癖を「行きたい」「やりたい」ではなく、「行きます」「やります」にしている。
ある程度の責任感は当然必要だし、僕も持っていますけど、最悪、できなくてもいいんですよ。ホリエモンからは1日1個くらいのペースで提案があるけど、いい話もあれば、「これはあんまりだな」って時もある。でも全部、やるって言います。
それでとりあえず走ってみるんです。走ってみた結果、面白くならなそうだったり、熱量が落ちてきたらやめてもいい。自然消滅することもある。でも大切なことは、まずは走ってみるということです。今の時代なにが当たるか分からない。
やっぱり誰だって、「それ面白そう、やります」とすぐに反応する人に黄金の企画を最初に持って行きたいと思いますから。
熱狂しなければ、やめればいい
――即決できないのは、「自然消滅は無責任」「やるやる詐欺になる」といった思いがあるのではそうですよね。ツイッターで、「自然消滅になってもいいんだよ」って書いたら、「それはダメでしょ」って反応が多くて。
「いいんだよそんなの」って思います。僕の場合、「あの話どうなった」ってことも多いですが、その時点で、その企画はダメなんですよ。当事者が飽きてる時点でそれまでなんです。
でも、そのプロジェクトに関わっている誰か一人でも熱狂したら、結果的に成功するんです。
だけどそれも、手を挙げて、とりあえず走ってみないと面白いかどうかなんて分からない。だから、とりあえずやってみるんです。「引き受けたら、最後までやらなきゃ」と思っていると、いい成果は出ない。
――義務感になりそうですしね
そう。「ちゃんとやらなきゃ」と思うと、いわゆるサラリーマン的な発想で進めてしまう。「こんな感じで仕上げておけば責任は問われないでしょ」みたいな。それが一番、周りもワクワクしないし、自分もワクワクしない。最悪ですね。一応やりきって、結果はまあまあみたいな。
本づくりでもよくありますよ。誰か一人がめちゃくちゃ本気になって売ろうとしていたら、だいたい売れるんですけど、「なんとなく売れそうだけど、だれも熱狂していない」みたいな時はだいたい、うまくいかない。そういう本って、みんなで会議して、みんなでなんとなく、「ありだよね」って感じで決まるんです。
コンテンツがヒットしたり、サービスが当たったりするかなんて最初からは分からないから、とにかくまずは立ち上げてみる。それで誰も熱狂していなかったら、やめちゃえばいいんですよ。僕の場合は、そんなことばっかりです。
広告会社からしても、広告主の担当者がきちんと「決める」ことをしてくれると仕事がしやすいと度々思うことがある。
自分の中の判断軸がなくて決められない人ってやっぱりいるわけで、色々提案しても、上層部がとか、今のお客さんがなど色々言い訳を作って守りに入ってしまうのもあったりする。
「即決」できる人が上司にいると、下は非常に進みやすいなと思うことも多々ある。
Action Learning、クイックウィンな視点で進まねば。
楽天のコンセプトである『スピード!!スピード!!スピード!!』という感じが個人的には好きだな。